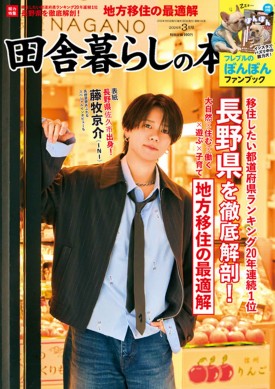5年前、約25年間空家だった父の実家へと移住した吉田智彦さん。吉田さん夫妻を待ち受けていたのは、住まいの確保=納屋をDIYで住居化でした。そして、半自給自足の暮らしを目指すなかで見舞われた3年前の豪雨による水害。自然とともに、常に前を向いて進む吉田さん夫妻の思いを寄せてもらいました。
掲載:2025年8月号
DIY未経験で納屋の住宅化に挑戦
吉田智彦(よしだともひこ)●ライター、フォトグラファー。子どものころから夏は両親の田舎で自然と親しんで育つ。20代は北極圏へ通って先住民の生活に触れ、30代は国内外の巡礼路を歩く。50歳で福井の田舎にある納屋を推定200万円で住居に改修。その様子はYouTube「のんびりいこうSimple life」に詳しい。https://www.youtube.com/@simplelife3834
福井県南越前町(みなみえちぜんちょう)
もともとあった窓は2階にひとつだけ。10カ所に新たな窓を設置しました。リビングは4連にして明かりを確保。(吉田さん 以下省略)
我が家は軒先1mと離れていないところに川が流れていて、心地よい水の音が居間にいても耳を楽しませてくれます。
家は、福井県にある父の実家。以前から半自給自足の暮らしをしたかった私は、コロナ禍で社会が閉塞感に苛まれていた令和2年に、神奈川からの移住を決意しました。妻のかおりは東京生まれの東京育ちですが、自然への憧れが人一倍強く、すぐに賛成してくれました。
ただ、母屋は約25年間無人だったために雨漏りがひどく、住める状態ではありませんでした。移住資金も充分になかったので、家の修繕は自分でやるしかありません。しかし、DIYも未経験。そこで白羽の矢が立ったのが、隣に立つ納屋でした。築60年以上の2階建てで、湿気で床は落ち、土壁はあちこちに穴が開いていました。それでも、母屋より小さいので何とかなるだろうと思ったのです。今振り返ると無謀でしたが、無知と未来への希望で突っ走り、1年半後の秋、ついに入居。それまで、課題にぶち当たるたびに途方に暮れたものの、友人が東京から駆け付けてくれましたし、好奇心が旺盛な地元の人と知り合うよいきっかけにもなりました。
改修前の納屋の1階。古い農機具がたくさん置かれていて、それらを取り除くと、床が崩れ落ちていました。
神奈川や新潟から駆け付けてくれた友人と、裏山の竹藪から切り出した竹で外壁を張るための足場づくり。
現在の納屋ハウス。住み始めてから2年経ちましたが、風呂場が完成したのは今年のこと。それまで、屋外でドラム缶の五右衛門風呂に入っていました。
水害で崩れた谷で、生物多様性に富んだ森づくり
住居が完成し、いよいよ半自給自足に向けて動き出そうとした矢先の令和4年夏、思いもかけないことが起こりました。
42時間に426ミリという観測史上最多降水量の雨が降り、家の前を流れる川が氾濫。土砂を大量に含んだ水が集落の半分近い民家を飲み込んだのです。被災後、たくさんのボランティアが泥かきや瓦礫の処理を手伝ってくれましたが、集落を離れなければならない人も出たほどの大惨事でした。
このとき、河川の護岸や道路などの公共設備は復旧の対象になりましたが、個人所有の山は対象外でした。その中に、崩れた土砂が民家裏まで迫った谷があり、二次災害の恐れがありました。居ても立ってもいられなくなった私は、小型重機やチェンソーを扱う資格を取り、山の整備技術を身につけて「福井かひる山風土舎」を設立。谷にあふれた土砂や流木を整理し、令和6年から生物多様性の専門家を招いて生態系レベルから豊かな森にしていく活動を始めました。
被災して3年が経とうとしている今も周辺では工事が続き、谷を囲む稜線で大規模な風力発電の開発計画が進められています。決してよい状況とは言えませんが「自然との調和を図りながら豊かに暮らすにはどうすればよいか」を考えながら活動しています。災害は気が滅入るような問題を浮き彫りにしますが、同じ思いを抱く人たちとの出会いが勇気をくれています。また、ここで体験していることは全国で起きている環境問題の縮図と思えるからでしょう。
今は、森の再生活動をしながら、罠猟や畑づくり、物書きをして暮らしています。本やネットでは知り得ぬ、あるがままの自然とその深淵な営みに触れる日々に魅せられながら。
崩れた谷の沢に石を積んで緩やかな流れを再生しながら土壌を安定させるワークショップ。グリーンインフラの技術を学ぼうと県外からの参加者も。
車で小一時間のところにある琵琶湖へ行き、仲間とカヤック。移住先で、こんなにたくさんの友人ができるとは思ってもいませんでした。
「南えちぜん森のがっこう」として風土舎で企画したジビエ教室。イノシシやシカの肉と地元の野菜を使って鍋とバーベキューを楽しみました。
家の周りに自生するドクダミの花とヘビイチゴをホワイトリカーに漬けて虫刺されの薬に。
生物多様性の森づくりに参加してみませんか!?
「風土舎では、『水の道再生プロジェクト@大桐』としてワークショップ形式で崩れた谷の再生を行っています。講師は生物多様性の専門家、坂田昌子さん。石積みやしがら組みなどの伝統工法で土壌の安定と緑化を促しながら、あらゆる動植物の拠り所にしていきます。年内は11月までほぼ毎月開催。老若男女どなたでも参加可能。興味を持たれた方は風土舎のFacebook(https://www.facebook.com/profile.php?id=61551003414845)から情報をご確認ください」(吉田さん)
文・写真/吉田智彦
この記事の画像一覧
この記事のタグ
田舎暮らしの記事をシェアする