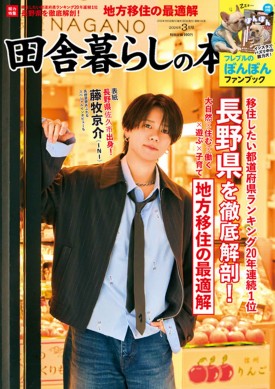「ウンチ」の可能性
ウンチの話をする前に、サツマイモの苗を植えた時の奮闘について書いておこう。まず苗を刺しこむ位置を深く耕す、次に左右に深さ30センチの溝を掘る。掘った土は畝に盛り上げカマボコ状とする。ビニールを広げ、裾を溝に落として土で固定する。かぶせたビニールに苗を刺しこむ。1本の長さ20メートルを5本。どれほどのエネルギーを要したかおわかりだろう。機械を使えば早いし綺麗な仕上がり・・・近隣の農家はみなそうだ。僕は無料の筋トレジムに行ったつもりで半分楽しみながらこれをやる。
排泄物から見えてくる生命の循環
ではウンチの話をしよう。偶然だが春以降三度にわたってウンチに関わるニュースを見た。最初は東京ドームシティーで開かれた「うんち展==NO UNCHI、 NO LIFE」。動物のウンチ150点が展示されたという。タヌキは複数の個体が同じ場所でウンチする。仲間との情報を得るためらしい。
僕にとって身近なミミズは落ち葉や土を食べて球状のウンチをする。そのウンチは隙間が多く、空気や水をよく通す。微生物の格好のすみかになり、アミノ酸やミネラルを多く含む。なるほど、ミミズがいっぱいいる畑の野菜はよく育つわけだ。作業中に枯草の下からにょろにょろ出て来るミミズ。手近にバケツがあればそれに、なければ作業ズボンのポケットに入れておく。水槽のウナギたちが美味しい食事を心待ちにしているのだ。
「うんち展」を監修した専門家は言う。
うんちはただの「臭い、汚い」排泄物ではない。うんちの役割を理解することで自然の不思議さ、生命のつながりを感じてほしい・・・。
「献便」と腸内細菌の重要性
次に僕が眼にしたのは献血ならぬ「献便」の話。潰瘍性大腸炎などの治療薬開発のため、順天堂などのベンチャー企業がウンチ提供の専用施設を設けた。人の腸内細菌は1000種。その絶妙なバランスで健康が維持されているが、抗生物質の過剰使用や動物性蛋白質、脂質の過剰摂取で腸内細菌が失われ、様々な病気が引き起こされる。そこで、健康な人の腸内細菌を患者に移植し、腸内環境を良好にする治療、それが「献便」というわけだ。
「野糞」という名の循環
そして、ウンチ談義の第三弾、真打の登場である。朝日新聞夕刊で「旧石器時代の旅」という5回連載がなされた。文化人類学者であり探検家でもある関野吉晴氏(76)は、使える道具は石器や自然にあるものだけという条件で新潟県の集落に小屋を建てる。そして言う。
人間が自然の時間をいじって旬も関係なく野菜や果物が食べられるような現代のほうに違和感を覚える・・・。
関野吉晴氏は「うんこと死体の復権」というノンフィクション映画の監督を務めた。ミニシアターで評判を呼び、全国各地で上映が続くその映画に、半世紀以上にわたって野糞を続ける「糞土師」が登場する。朝日新聞の記事には野糞に「のぐそ」とルビが振ってある。目にした瞬間、良くも悪くも「野蛮」なこれは響き、この言葉ほど都会生活から遠い隔たりを持つ言葉はないだろうなあ・・・僕はそう思った。
野糞の主は元キノコ写真家である伊沢正名氏(75)。茨城県桜川市で親から引き継いだ自宅の命名は「糞土庵」。なんと、野糞をするために裏山「プープランド」を購入したというのだからすごい。プープは英語圏の子供が使う排泄物、すなわちウンチのこと。
伊沢氏は山歩きの途中で真っ赤なキノコに出会う。美しさと成長ぶりに感心し、調べてみると菌類は枯れた植物や動物の死骸を分解し、栄養にするだけでなく、土を肥やし森を作る働きをしていることを知る。「命をつなぐというのはこういうことなのか。人間だけが排泄物を臭い汚いと、ほかの生き物と切り離して始末している」。それならと、1974年1月1日、伊沢氏は野糞生活を始めたのだという。
→ ウメは収穫後半になると木に登らずとも勝手に落ちて来る。前半は青梅だった。そして今は赤いウメ。ハチミツと合わせて煮る。すこぶる美味。朝食のパンによし、晩酌ワインのつまみによし。2時間で出来るところもせっかちの僕にはいい。
映画の中で伊沢氏は、野糞を埋めた場所に枯れ枝を立てて目印とし、掘り返して観察する。そして言う。「野糞をしていない場所と比べれば、草木の育ちは歴然としている」とも。僕自身の野糞は・・・穴が掘ってあるので目印の棒を立てておく必要はない。折に触れて抜き取った草や剪定枝を小さく刻んで投げ込む。この精神、はなはだ野蛮である半面、衛生観念は優れている。雨水を貯めるタンクと石鹸が何か所にも置いてある。僕は手を常に清潔に保つ。
命のつながりへの気づき
長々とクサイ話を書いたのは田舎暮らし46年という僕の原型がそこにあるゆえだ。小学生の頃から、ドブ、堆肥置き場、ゴミ捨て場、他の人が避けるような所を掘り返し、でんでん虫、ハサミ虫、ミミズなどを集めるのが好きだった。「命をつなぐ」といった難しいことが分かる年齢ではなかったが、汚い所にも元気よく暮らす生き物がいるのだということをそこで知った。誰もがするウンチ。しかし、用をすませ、大きな音とともに洗い流したそのモノは、どこに行くのか、最後はどうなるのか、考える人は多くはあるまい。
だいぶ前に読んだ本のことをここで思い出す。戦後、駐留米軍兵士が母国で食べていたレタスを恋しく思う。近くの農家に栽培を依頼しに行った、そして知る、肥料として人糞を使っていることを。そんなものはやめなさい、化学肥料を使いなさい・・・。これが日本における化学肥料普及の先駆けとなったのだという。まさかナマのまま使うはずはない。長期間発酵させていたはずだ。それでも“先進国”の人の目には野蛮、汚いと映ったのであろう。
僕がスコップ仕事を始めると必ず鶏が近寄って来る。知能はかなり高い。僕の手にあるスコップ=ミミズや昆虫、その思考が働くのだ。旧石器時代への旅、その連載第四回には「土に戻りつながる命」というタイトルが付いていた。まさにこの場面がそうである。
ピーマンの苗を植える1か月前、スコップで削り取った草を大量に積み上げ、米ぬかと鶏糞のミックスを混ぜ込んでおいた。そこには食べ物があり、直射日光が遮られ、ほどよい湿り気が保たれる。ミミズにとってのパラダイスなのだ。僕の後を追って来た鶏は10センチもあるミミズをひと呑みにし、その合間にウンチする。我がウンチ、鶏のウンチ。地中のミミズたちはそれをエサにさらに繁殖してくれる。野菜にはエネルギーを。命から命への小さな循環である。
この記事のタグ
この記事を書いた人
中村顕治
【なかむら・けんじ】1947年山口県祝島(いわいじま、上関町・かみのせきちょう)生まれ。医学雑誌編集者として出版社に勤務しながら、31歳で茨城県取手市(とりでし)に築50年の農家跡を購入して最初の田舎暮らしを始める。その7年後(1984年)の38歳のとき、現在地(千葉県八街市・やちまたし)に50a(50アール、5000㎡)の土地と新築同様の家屋を入手して移住。往復4時間という長距離通勤を1年半続けたのちに会社を退職して農家になる。現在は有機無農薬で栽培した野菜の宅配が主で、放し飼いしている鶏の卵も扱う。太陽光発電で電力の自給にも取り組む。
田舎暮らしの記事をシェアする