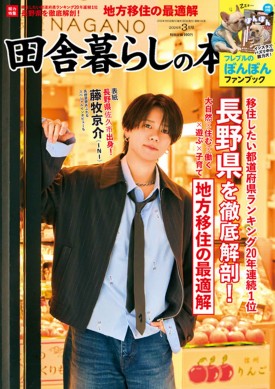精神科医が抱える「何者にもなれない」悩み
キャリアと夢のはざまで苦しむエリートたち
朝日新聞「悩みのるつぼ」に相談を寄せたのは30代女性。なんと優秀な人、立派なキャリアの人。そんな人がなぜ悩むのか・・・我が第一印象だった。すなわち、この女性は、絵、漫画、小説などの分野で活動したいと子どもの頃から思っていた。大学はいったん理工学部に入ったのだが、”夢を追って貧乏になるのは嫌だと思い”、医師である父の勧めで医学部に入った。そこでは楽しく、成績も優秀だった。
現在は精神科医です。最近また小説家になりたいと10万字程度の物語を書きました。まだ発表もしていませんが、他人の発行部数や知名度がうらやましくて、嫉妬で身が焼かれそうになります。自分にしか出来ない何かで早く周囲に認められたいという強迫、焦りで毎日息苦しいです。何者にもなれない、医者のままで人生が終わるのだと絶望的な気分になることもあります・・・。
20年ほど医学雑誌の編集に携わった僕は、医者はとびぬけたエリートなのだとの思いが今もあるが、この女性は違うのか。僕がもし精神科医なら彼女に言う。募る嫉妬心は体にとても悪いです・・・。
人間、進もうと決めた道では努力を重ねるしかない。他人と比較し、落胆したり妬んだりするのは時間とエネルギーの無駄だ。昔こんなことがあった。毎年秋に行われる出版社のロードレース大会は皇居2週、およそ10キロだった。40数年前の僕は1キロを3分20秒くらいで走っていた。そんな僕がどうしても叶わない相手がいた。くやしい、彼になんとか勝ちたい。努力を重ねた。しかしキロあたり5秒という差を縮めることは出来なかった。今年も負けたなあ・・・でも、全力を傾けたのだから素直に負けを認める。同時に勝者に敬意を表する。これが大事。
夢を追うには「貧乏を恐れない心」が必要?
まだ若い精神科医の女性には負けに耐える心も大事だと教えてあげたい。ただひとつ彼女の言葉で僕は気になる。「夢を追って貧乏になるのはイヤ」という部分。彼女の唯一最大の弱点はここではあるまいか。夢を追う、そのために貧しい暮らしになってもかまやしないわ・・・いかなる道を選択するにせよ、この気持ちが力となり、成功への第一歩になる。
今の我が暮らしを「成功」とは言うまい。だが夢を追ってビンボーになることに僕は平気だった。思い描いた夢が、一気にではなく、ポツリポツリと現実のものとなる。そのプロセスを楽しむ。思わぬ障害をなんとかはねのける、その苦労をも楽しむ。そこには嫉妬も焦りもなく、仕事を終えて浸かる風呂がただ心地よく、夕食がすこぶる美味い。田舎暮らしという夢は小さい。でも小粋な味わいを秘めているのである。
日中の光はキビシイ。しかし朝一番の風にはかすかに秋がある。オクラの花が心地よさそうに咲いている。ただしそれも一時のこと。昼前にはもくもくと雲が立ち上がり、やがて雷鳴と強い雨。ここ数日すっかりこのパターンになった。
猛暑だが、晴れ間にはあえて草取りで汗をかく。抜いたらすぐ枯れるようにするためだ。頑丈に根を張った土をプルパワーで引っ張る。しばしば切り傷を負う。あるいは爪の先端が割れる。そして、抜いた草の山が出来上がると同時に、草に隠れて見えなかった土が姿を現す。我がバッハは土の中にひそんでいる。そのバッハが姿を現す瞬間だ。
孤独と音楽、バッハに救われた人々
孤独 バッハと生きる
ドイツのバッハ資料財団で広報を担当する高野昭夫さん(64)を「孤独 バッハと生きる」と題して紹介したのは読売新聞だった。楽譜は読めず、楽器も弾けない。そんな高野さんは、孤独の中で出会ったバッハの曲を心の支えとして人々に助けられて道を開き、ここまで生きてきたという。
母親は富山の歓楽街でバーを営み、彼氏の所に行くことが多く、いつ親に捨てられるんだという恐怖があった。本当の父親は誰なのか知らない。そんな高野さんがバッハに出会ったのは中3の時。ずっと図書館に通い、バッハを聴き続けた。そして言う、「あの時出会えていなかったら今日まで生きていなかったと思います・・・」。
僕は激しいリズム、テンポの速い音楽、それが若い頃から苦手。暗く、緩やかで、沈み込むような音楽が好き。焼け付くほどの太陽の下で裸で畑仕事をする僕は、友人・知人から野蛮人、原始人とも呼ばれるが、こと、音楽に関しては間違いなくネクラな男のようである。
土を掘ると響くG線上のアリア
田舎暮らしとバッハはコインの表と裏。僕にとっては両者がピタッと重なり合う。草を抜き終えたら鍬を打ち込む。表面は白く乾き、熱くさえあるが、30センチの深さの土は黒く、水分が保たれている。そこからバッハが聞こえてくる。トッカータとフーガ、G線上のアリア・・・世間では熱中症警戒アラートが発せられる36度という午後の光。それに後頭部を焼かれながら、不思議と心は涼やかなのである。田舎暮らし、それはゆるやかに、静かに流れる音楽のようなものだ・・・ビートのきいた激しい音楽が好きという田舎暮らし実践者もいるかもしれないが、やはり僕はそうなのである。
この記事のタグ
この記事を書いた人
中村顕治
【なかむら・けんじ】1947年山口県祝島(いわいじま、上関町・かみのせきちょう)生まれ。医学雑誌編集者として出版社に勤務しながら、31歳で茨城県取手市(とりでし)に築50年の農家跡を購入して最初の田舎暮らしを始める。その7年後(1984年)の38歳のとき、現在地(千葉県八街市・やちまたし)に50a(50アール、5000㎡)の土地と新築同様の家屋を入手して移住。往復4時間という長距離通勤を1年半続けたのちに会社を退職して農家になる。現在は有機無農薬で栽培した野菜の宅配が主で、放し飼いしている鶏の卵も扱う。太陽光発電で電力の自給にも取り組む。
田舎暮らしの記事をシェアする