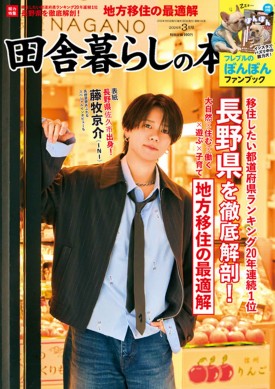自給生活が教えてくれるシンプルな幸福
プレゼンティーズムとアブセンティーズム・・・知らなかったな、この言葉。
手を動かす喜びと成果の実感
今年初めて本物の秋を感じる天気の1日であった。湿度が低い。光に濁りがない。起きた時ひんやりしていたので長袖のセーターで7時20分、ランニングに出た。しかしそれでも寒いと感じた。だがこひ太陽が高くなるとまだ気温は高くなる。今日はまずネギの移植から。太陽の位置が変わり、日陰の時間が多くなる場所から移し替えるのだ。収穫は来年1月以降になる。
続いて人参のタネまき。これまで4回タネをまいた。1回目は高温でやられ、2回目、3回目は激しい雨に叩かれ、発芽率は芳しくない。例年であればもう遅いのだが、高温傾向は10月まで続くというから大丈夫であろう。
例のごとく、我が物顔に繁茂した草の撤去からである。まず、手で抜けるものは抜く。スコップで取れるものは取る。そして最後は重い4本刃の鍬の登場である。これをフルパワーで打ち込むとほとんどのツワモノ草も掘り出せる。それを最後はベルト状にして引きずるのである。次は土に手を入れ、大中小の根っ子を根気よく探り出す。
タネをまきおわったらこの下の写真のごとく、ブルーネットで囲う。他の農家にはない手間がひとつ増える。耕したばかりの土にニワトリたちは興味を示す。引っ掻き回す。それを防ぐためだ。大鍬を使っての荒起こしからブルーネットで囲うまで2日がかり、のべ10時間の作業だった。
メンタル不調の損失は巨額
今日の朝日新聞夕刊でこの記事が目にとまった。出勤していても心身の不調で本来のパフォーマンスを発揮できない状態をプレゼンティーズムと呼び、病気などによる欠勤はアブセンティーズムと呼ばれるらしい。そしてなんと、メンタルに不調を抱えながら働くことによる損失はGDPの1%強、年間7兆6000億円にも達するのだと、横浜市大と産業医大の研究チームが推計した。メンタル不調による欠勤での損失は3000億円で、プレゼンティーズムの損失はその25倍にもなるというから驚く。
情報処理は増え、会社員の作業現場はどんどん複雑化している、大変なんだろうなあと、会社の仕事を離れて40年の僕にも想像がつく。メンタル不調のままにそうした仕事に取り組むのはキツイだろうということも想像がつく。
その点において、田舎暮らしの自給生活はじつに単純明快、お粗末と言ってもいいくらいだ。だ。僕が現役サラリーマン時代にはパソコンというものはなかった。今はおそらく10中8・9の人がパソコンを道具として仕事をこなしているのではないか。
田舎暮らし、自給生活は、あえて言えば単純作業そのもの。すべての行程がシンプルに進行してゆく。自分の手や足を使った作業の成果をリアルタイムで確かめられる。こりゃまずいと思ったらすぐさま軌道修正できる。作業の進捗状況が具体的な姿として自分の視覚で常に捉えられるところがいい。相手は生きた姿で目のすぐ前にいる。パソコンを通しての作業とは、おそらくここが違うのではないか。
人参の種まきと作業の流れ
例えば上に書いた人参のタネまき。面積およそ30平方メートル。ここを覆っている草をまず取り除く。軽トラ一杯分ほどの草だから時間はかかるが山盛りになった草で仕事の成果を実感できる。長い間に草の中にはゴミも混じる。手直かに用意したゴミ袋にごく小さなゴミも見逃さず投げ込む。土に混じる小石も見逃さない。
大まかな整地が終了したら、じっくり腰を下ろし、土の中に残る枯れ枝や根っこの切れ端を深く手を入れてつまみ出す。さらに表面を撫でるようにして浮かび上がったゴロ土を指で砕く。これで準備完了。タネを落とす。人参は好光性といって深く埋まると発芽率が悪くなるゆえ、薄く土を掛けてやる。そして最後にネットを張るわけだ。
前にも書いたが、田舎暮らしの自給生活とは立案から現場作業まで一貫して自分の頭と力を使う、言うならば”単純わがまま仕事”。失敗の責任は自分で取る。成果報酬も自分が得る。人参はひと雨あれば10日ほどで発芽する。発芽後は間引きと土寄せをやって成長の過程を自分の目で確かめる。収穫は年が変わって連日霜の降りる頃だ。作業工程から収穫まで、さほど気持ちが高ぶるわけでなく、もちろん気分が落ち込んで仕事の効率を落とすということもない。
この記事のタグ
この記事を書いた人
中村顕治
【なかむら・けんじ】1947年山口県祝島(いわいじま、上関町・かみのせきちょう)生まれ。医学雑誌編集者として出版社に勤務しながら、31歳で茨城県取手市(とりでし)に築50年の農家跡を購入して最初の田舎暮らしを始める。その7年後(1984年)の38歳のとき、現在地(千葉県八街市・やちまたし)に50a(50アール、5000㎡)の土地と新築同様の家屋を入手して移住。往復4時間という長距離通勤を1年半続けたのちに会社を退職して農家になる。現在は有機無農薬で栽培した野菜の宅配が主で、放し飼いしている鶏の卵も扱う。太陽光発電で電力の自給にも取り組む。
田舎暮らしの記事をシェアする