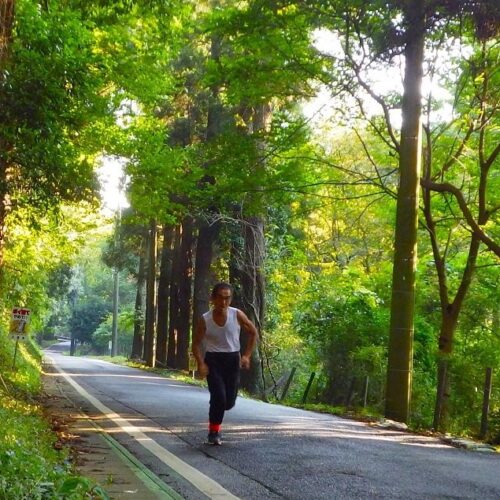近頃、暗い話が多いなあ
と言うと、いや昔も今も変わらないさ
暗い話は前からあったぜ
そう感じるのはアンタが年取ったせいだよ
そんな声も聞こえるけれど・・・そうかなあ
フラレた腹いせに包丁を持ち出す男なんて
昔はいなかった
女にフラレても昔の男は
安アパートで悲しみにただ耐えた
テレビのコント55号の笑いでごまかしながら
悲しみに耐えていた
少女を盗撮したり自分のモノを出して見せたり
フェイクニュースを流したり
他人への攻撃に走ったり
スマホという道具はここまで男を(時に女をも)
指先ひとつの軽挙に走らせてしまうものなのか
おーいみんな、特に男たちよ
汗から遠い、肉体疲労から遠い、忍耐から遠い
動物としての生きる感覚からもまた遠い
年寄りの戯言と取られてもいい
日々、土の上で暮らすスマホを持たない
泥と汗まみれの老人は思うのだ
近頃の世の中やっぱり暗い話が多すぎる
もうちょい楽しく陽気に生きなくちゃ、と
CONTENTS
秋の畑で見つけた小さな発見
10月が1週間過ぎて、あの猛暑は遠い過去の夢みたいな感じになった。ここ数日、雨多く、日照少なく、最高気温は27度止まり。朝の最低気温は20度を割る。それでもって僕は連日、防寒対策に奔走している。毎年のことなのだが、ナス、ピーマンは低温を遮断してやると師走の頃まで収穫が可能となる。それに今年はゴーヤも加わった。
ゴーヤに関してはひとつ発見した。3か所に分けて作り、2か所は皆さんおなじみの緑色。そしてもう1か所は白いゴーヤ。緑のものは終わったのに、白い方は今もって実を着け、けっこう大きくなるのだ。
ナスやピーマンを守る防寒対策の工夫
ナスとピーマンの防寒は使い古しのパイプ、使い古しのビニールをなんとか組み合わせてそれらしい姿とする。トップの写真がその作業スタートの様子だ。ビニールは何枚ものつぎはぎゆえ完全密封とはならない。しかし、晴れたら完全密封では高温になりすぎるゆえ、つぎはぎの一部から空気が抜けるくらいが今はちょうどよい。ただし夜はやはり冷える。その対処として特大の、使い古しゆえにほとんど光を通さないビニールをすっぽりかぶせる。朝になったら外す。
今日はそんな苦労の末に完成したピーマンのハウスに入ってゴソゴソ仕事をした。ピーマンの背後に1メートル弱の空間がある。そうだ、ここにキャベツの苗を植えよう。ポットまきの苗はまだ7センチと小さいが、小さい苗にとっては露地よりもこのハウスの中の方が後の成長には好都合に違いない。
心と体のバランスを保つ暮らし
汗を流すことで心も整う
心と体はぐるぐる回る円
涼しくなったと書いたばかりであるが、今日の日中はかなり蒸し暑かった。エンドウの収穫が終わった7月以来使わずにいたビニールハウスに草取りと整地のために入ったせいでもあるが、何日ぶりかでドドッと汗が出た。エンドウのツルを巻かせた長い竹が数十本もある。それを片付けてから大量の草を抜き捨てるのだが、エンドウなき後、ヤマイモがその竹を間借りして巻き付いている。
ヤマイモ掘りがくれる小さなワクワク
地下にあるヤマイモのサイズはツルの太さでわかる。直径1ミリは小。2ミリは中。3ミリになると両手で引っ張っても切れないほどに頑丈で、地中から出るイモはたいてい長さ60センチくらいの大物だ。こいつを掘り出すのにはかなりのエネルギーを使うが、しかし、さて、どんな姿のイモが顔を出すか、ちょっと気分がワクワクする。
若返りのホルモンは、自分の心と体で作るものよ!
身体って想像以上に心に左右されるもの。毎日の暮らし方でホルモンの分泌も変わるはず。ワクワク、ドキドキが有効。サプリに頼らない!
加藤登紀子さんの「ひらり一言」からの引用である。僕も前からそう思っている。体内ホルモンは心の働きと相関し、体に影響を与える。そして心地よく稼働する肉体は良質なホルモンの産生を促す・・・すなわち円形の循環であると思っている。我が日常におけるワクワクドキドキ、それは日々どれも微小なものであるが、途切れることなく存在するところがいい。
土や虫や鳥にワクワクドキドキする少年だった。三つ子の魂百まで・・・その集大成が今の百姓暮らしなのである。サプリメントに無縁。テレビのCMで、たった小さな1瓶の、たった3粒の、サプリらしきものを口に入れ、それまでのうなだれ姿からスーパーマンにでもなったごときパワフルを演じて見せる。それを、僕は、そんなのあるわけないでしょ、ひとり笑っているのである。
喜びを感じる力が人生を豊かにする
「木の実」が落ちてくるような生き方
よろこべばしきりに落つる木の実かな 富安風生
読売新聞「編集手帳」で目にした句。「喜んで笑顔になっていると、木からどんぐりなどの実がどんどん落ちてくる――そんなことあるはずないのだが、どこか楽しい」筆者はそう書く。同感である。小さなことでも、素直に喜んでいれば「木の実」はどこからか落ちてくる。しかし昨今の世間では、喜ばないで怒る、怒りを他人にぶつける。SNSでのフェイクニュースや他人への攻撃はその一例であろう。仕事は面白くないし、物価は上がるし、女にはフラレるし・・・それを不機嫌の理由にするのかもしれないが、それではいつまでも「木の実」は自分のそばに落ちて来ないのである。
田舎で暮らす知恵と人間関係
数日前、この上の写真の防寒壁を作った。初めはニワトリの侵入を防ぐだけで、ブルーネットの障壁にするつもりだったが、待てよ、ニワトリ侵入とともに、北風の吹込みも阻止すれば野菜の成長を促進するのではないか・・・それでもって、まともな使い方はもはやできないごわごわのビニールを総動員し、ごらんのような壁を作り上げたのである。
今日はそこにキャベツの苗を植える。総数200。この場所に植えられるのはそのうち100くらい。陽が暮れるまで頑張った。小さな苗を土に埋めながらふと思った、スマホを片時も離せない若者にこの作業を経験させてみたいと。
これも年寄りの戯言になるだろうが、彼らの虚弱化がじわじわと進んでいるような気がするのだ。学校でのプール授業は取りやめ、体育の授業は冷房のきいた体育館でやる・・・たしかに異常な高温への夏の対策としては優しい心遣い、妥当な一面もあるだろう。が、そんな肉体への負荷を避ける一方で、指先ひとつで全てがかなうスマホに若者が費やす時間は膨大と聞く。これでは、時に冷酷となる自然と向き合い対抗する、その力はどんどん減ってしまうのであるまいか。
移住者支援が進む宮城県七ケ宿町の挑戦
さて、メディアはノーベル生理学・医学賞を受賞した坂口志文氏を大きく伝えている。その喜びから間を置かず、今度は北川進氏の化学賞受賞も伝えられた。そのニュースに触れて僕がまず思ったこと。東の東大、西の京大と阪大。東と西の両者はともすれば昔からライバル関係とみなされてきたが、自然科学分野での評価はどうやら西に軍配が上がる。
若い頃僕は『免役』という雑誌の編集に関わった。この雑誌の創刊に大きな力を及ぼしたのは当時、大阪大学の総長だった山村雄一氏で、2018年にノーベル生理学・医学賞を受賞した本庶佑氏も阪大在籍時に雑誌『免役の』企画に尽力されていた。
坂口氏の受賞をテレビで知った時、僕がすぐ思い出したのは編集部時代にしきりと使われていたサプレッサーT cell(抑制性T細胞)だった。だがそれは分子同定がされずいつしか消えてしまったとのこと。今回の坂口氏の発見は「制御性T細胞」と呼ばれる。人体の免疫機能は生体防御の役割を果たす。しかし時には、癌細胞などの外敵だけでなく正常な細胞までもやっつけてしまう。これが自己免疫疾患と呼ばれるものだが、坂口氏の研究は、正常な細胞まで傷つけてしまう免疫の働き、それを部分的に抑制する、すなわち、T細胞がマイナス行動をしないようにコントロールすることができるというものだ。
20年住んだら戸建てあげます
風に揺れる木々の音で6時ちょっと過ぎに目が覚めた。まさしく今、伊豆諸島周辺で荒れ狂っている台風22号の影響が千葉にも及んでいる。早々に朝食をすませ、風の影響はどの程度か、見回って確かめる。だいぶ傾いた屋上庭園には過日、数本の孟宗竹を噛ませてさらなる傾きを防止したが、まだ不足かな、あと2本ほど足してやろう。
伊豆諸島での瞬間最大風速は70メートルだという。僕は59メートルを経験したが、70メートルは想像に余りある。築44年の我がボロ家なんか真っ先に倒壊してしまうだろう。そんなこんなを考えながら強風対策をしていて、昨日の朝日新聞夕刊の記事がふと思い出された。
宮城県七ケ宿町。人口1200人。移住者を呼び込むため小さな自治体はさまざまな手を尽くすが、これほどの「厚遇」をもって呼びかける例は珍しい。給食費、保育料、18歳までの医療費は無償。出生時や小中高への入学時に贈られる支援金は第一子30万円、第二子50万円、第三子70万円。ガソリン代を補助する給油券もある。
そして極めつけは住宅。新築の町営住宅の家賃は3万9000円。そこに20年住み続けたら土地建物とも居住者のものになる。かくして移住者は町の人口の2割、235人に及ぶという。この10年で移住者から生まれた赤ちゃんは21人、現在の保育園児30人のうち移住者の子は19人だというから日本の人口減少にも貢献している。
万事喜ばしいことばかりだが、皮肉な面もある。町出身の若者の多くは進学や就職で町を出たまま戻っては来ない。つまり、町の人口維持は移住者によるものだという。そして・・・ああ、ここでもかと、僕が少しため息をついたこと。移住者に対して、元からの町民の印象は「何をやっているかわからない人たち」、さらには「町の『担い手』と言うけれど、町の支援策で担ってもらってるだけじゃないか」との陰口もあるらしい。
地元住民と良好な関係を築くコツ
以前書いたことがあるけれど、移住者にとって単純かつ重要なことは、地元の人と道で出会ったら大きく朗らかな声でこちらから先に挨拶することである。その挨拶をきっかけとして、いきなりではなくとも、だんだんに、互いの身について語り合うことになろう。僕は最初の田舎暮らしでも、現在の田舎暮らしでも、必ずそうした。黙って通り過ぎるなんて絶対禁物。ランニングの途中で行き会う村人には必ずスピードを落としておはようございます、暑いですねえ、やっと涼しくなりましたねえ・・・軽く頭を下げ、そう言葉を発してきた。そうすれば「何をやっているのかわからない人・・・」なんて疑念なぞ生じることはない。田舎暮らしを成功させるコツ、それはなんともシンプル。朗らかな声での挨拶、保育園児の朝礼みたいなものだ。
移住先で暗い人間だという印象を持たれたらアウト。明るく振る舞う、新しい場所での出会いを喜ぶ。さすれば「木の実」がどんどんアナタの足元に落ちてくる。何事も慣れなのである。
挨拶から始まる信頼づくりの力
大学の運動部時代、通りの遠くで見かけた先輩に、どうせ向こうからは見えていないだろうと挨拶しないでいると後でビンタを食らった。でもって、例えばJRお茶の水駅周辺の雑踏の中でもチワッ、シマスッと大声を出した。そばを歩いている人の心臓には悪かったであろう。しかし、少年時代、どちらかというと内向的だった僕なのに、道で大きな声を発することに躊躇しない。60年前の無茶苦茶な運動部体験が我が田舎暮らしをいま助けてくれている。何事も慣れである。壁をすり抜けたらあとはスンナリなのである。
働くことは“退屈しない人生”の秘訣
臨機応変の優れた男か、行き当たりばったりのダメ男か
冷たい雨の1日であった。なんと日中の気温は17度。最低気温でも27度だったあの夏が懐かしい。全身濡れて、寒さがしみるがやるべきことはいろいろある。もし神様が、我が日々の生活を空から眺めてくれていたら、なんと言うだろう。臨機応変、テキパキと仕事をこなす立派な男・・・逆に、万事行き当たりバッタリ、しょうのない男だねえ・・さてどちらであるか。
予定通りにいかない日々こそが面白い
明かりを消してベッドで眠りに落ちるまで、あるいは毎朝ランニングしながら、今日明日の仕事はABC・・・その段取りを頭の中で考える。しかし、その通りにいくことはほとんどない。飛び込みの作業が必ず生じるからだ。例えば今日、ニンニクを植える場所の整地のためにスコップを手にして向かったが、その途中、ニワトリたちに踏まれて倒れているネギが目に入る。起こして土を寄せてやった。
そして前進。今度は土が浅すぎる秋ジャガが見える。手にスコップがあるゆえ、ついでにやれる、土盛りしてやろう。と、その近くのヤブで、カナムグラに蓋をされた格好の支柱数本とネットを留めるピンが何本も見える。ああ、これ使えるな、昨日半分まで仕上げたレタス苗を植える予定の場所に使えるな。それで終わりじゃない。よっしゃ、どうせならこの厄介者のカナムグラを一気に始末してしまおう・・・。
思いつきから生まれる畑仕事の楽しみ
と、まあ、こんな感じで、当初の予定、ニンニク植え付け場所にはなかなか辿り着けない。さりとて、この当初の予定をパスするわけでもない。取り掛かる。途中のあれこれで遅れたぶん、スピードを上げてやる。ランチ前に終わらせる予定がもしダメなら、いったん荷造り仕事に精を出した後、再び日暮れにニンニク予定地に飛んでいき、暗くなっての視界不良であろうとも、なんとか当初予定の帳尻を合わせる・・・。
我が百姓暮らし、台本があってないようなもの・・・ほとんどアドリブ。でもいいのさ、アドリブでも。今日なした仕事の総量がきっと明日につながる、思えば、起きてから夕刻風呂に浸かるまで、自分の体が静止するのはランチタイムの30分と、荷造り途中のティータイム10分間だけ。巣穴に出入りする蟻のごとくの徘徊だらけだ。もちろんボケゆえの徘徊じゃでなくてネ。
アドリブ的な労働が人生を動かす
フフッフ、この上の写真も、行き当たりバッタリ仕事の一例である。毎年今頃レモンに防寒を施してやる。今日、傷んだ木枠を修正していて、ふと思いついた。けっこう余剰スペースがあるな。よし、レタスをここに植えてやろう。例によってブルーネットはニワトリの侵入防止。思いついてからレタスを植え終わるまでに3時間。朝からずっと雨。体がだいぶ冷えてきた。でも満足する、濡れながらの仕事は寒いが案外心地よいのである。
ファーブルとハキリバチが教えてくれること
労働というものが、人生を陽気に過ごすための最良の方法であるならば、退屈なぞ感じることなしに過ごしたのにちがいない
10月も気温は高い・・・9月の初めに気象庁はそう発表した。しかしハズレである。台風が2つ続けて発生し、雨が多かったせいでもあるが、気温は上が20度ちょっと、下が16度。気温そのものは平年並みかもしれないが、日照時間は圧倒的に少ない。25枚の太陽光パネルがしょんぼりしている。
とりあえず、暑さでずっと不調だったキャベツ、白菜、ブロッコリーは喜んでいるが、ナス、キュウリ、ピーマンなどは不満げな顔をしている。バナナもそうである。10月が高温ならばハウスに収めるのは11月でいい。そう考えていたけれど、最低気温が16度では成長が止まる。それで急ぎ8本の鉢植えバナナをビニールハウスに収めた。
掛けてあるビニールは2枚。夕刻に下までおろし、朝になったらこの下の写真のように太い竹で押し上げて光を入れてやる。さらに、5度以下になったらアウトであるバナナをいずれ零下になる低温から守りたい。太陽光発電に電気カーペットをつないで保温してやろうと考えている。これから来年3月まで、寒さ対策としてやるべき作業は夏の倍ほどになる。
小さな虫の大きな努力に学ぶ
さて、上に掲げた「労働というものが人生を陽気に過ごすための最良の方法であるならば・・・」は天声人語で目にしたものだ。天声人語の筆者はハギの葉に丸い穴があいているのを目にする。ハキリバチの仕業であるらしい。
ハキリバチはあごでハギやバラなどの葉片を切り取り、竹筒や地中へ運んでコップ形の巣をつくる。葉の穴部分は建材になったわけだ。雌のハチが単独で巣をつくり、花粉と蜜で団子をこしらえ、その上に産卵する。最後に葉片でふたをすれば子ども部屋のできあがりだ。幼虫は団子を食べ、ふたを食い破って羽化するという・・・。
へえっー。小さいころからの虫好きである僕は感心する。すごいなあ・・・命あるもの、さまざまな努力をして生きている、次の世代に命をつなぐ。ばかりでなく、この努力を楽しんでやっているようにも思えるではないか。さて、そして、天声人語の筆者はさらなる知見を得るため『ファーブル昆虫記』にたどり着く。そして出会うのだ、ハキリバチの仕事に感銘を受けたファーブルの言葉に出会う。
田舎暮らし40年、退屈しない理由
労働というものが、人生を陽気に過ごすための最良の方法であるならば、退屈なぞ感じることなしに過ごしたのにちがいない。
田舎暮らし40年余。ずっと走り回って生きてきた。結果、僕もハキリバチに似てしまったか。退屈したことがない。ちょっとキザだが、我が辞書に退屈という言葉がない。世間には「ゆとり」という言葉がある。走り回っているばかりじゃダメ、人生、ボッーとしている時間が必要、大切、そう唱える人もいる。
「ボーッとしない人生」は幸せかもしれない
幸か、あるいは不幸か、僕はボッーとすることがない。日々労働に追われて暮らす。当然ながら、思うように事が運ばず難儀する作業もある。しかしそれが退屈を押しやる。次々と生じる作業をこなし、100点満点の70点ほどであっても、ともかくどれもそれらしく仕上がったという満足を得る。人生を退屈せず、陽気に過ごし、うまいメシが食える、深く眠れる、お通じもよろしい・・・これらをもたらしてくれるのが労働なんだということを知る。
冒頭、昨今の世間には暗い話が多いと書いたが、ズルして、ラクして、手っ取り早く金儲けしようという人間も多い。うちにもさまざまなメールがくる。お使いの○○カードに不審な使用がありました。お使いの××カード更新が明日となります。いつもJAバンクをご利用いただきありがとうございます。ただいまJAではお客様情報を確認しておりまして・・・等々。ふふっ、いろいろやるものだねえ。途切れることなく悪知恵が浮かんでくるものだねえ。すまんが俺はその手には乗らないよ。
あるいは電話が鳴ることもある。こちら総務省通信局のなんとか、かんとかです。この電話はあと1時間ほどで使用できなくなります。つきましては・・・と女の声が言う。彼らは間違いなく人生の持ち時間を無駄に費やしているね。ハキリバチの爪の垢でも煎じて飲ませてやりたい。
心を温める“矛盾の暮らし”を楽しむ
体は冷えても心は温かい
今日10月15日。夜来の雨はかなりの量で、ランニングに行く時は止んでいたが、再び断続的に降り始めた。雨に叩かれ傾いた白菜やキャベツに助けの手を差し伸べるため畑に向かう。厳しい夏であった。そして、穏やかな秋晴れはほとんどなしに、早や初冬の雰囲気さえ漂う今日。
8月植えの白菜、キャベツ、ブロッコリーは半数が死んだ。そして今、生き残った半数がようやく大きくなった。本当はもっと光があると嬉しいよなあ・・・そう囁きかけながら僕は株元に手を入れて空気の通りを良くしてやる。人生を退屈せず陽気に過ごさせてくれる、それが労働。空気は冷たい。濡れた体が冷える。でも不思議と気持ちはあったかいのである。田舎暮らしとは、体の冷たさと心の温もり、絡み合ったそれが二重のらせん状となり空にゆるゆる登って行くもの・・・。いかがです? アナタも、この奇妙な“矛盾生活”に身を置いてみるのは。
この記事の画像一覧
この記事のタグ
この記事を書いた人
中村顕治
【なかむら・けんじ】1947年山口県祝島(いわいじま、上関町・かみのせきちょう)生まれ。医学雑誌編集者として出版社に勤務しながら、31歳で茨城県取手市(とりでし)に築50年の農家跡を購入して最初の田舎暮らしを始める。その7年後(1984年)の38歳のとき、現在地(千葉県八街市・やちまたし)に50a(50アール、5000㎡)の土地と新築同様の家屋を入手して移住。往復4時間という長距離通勤を1年半続けたのちに会社を退職して農家になる。現在は有機無農薬で栽培した野菜の宅配が主で、放し飼いしている鶏の卵も扱う。太陽光発電で電力の自給にも取り組む。
田舎暮らしの記事をシェアする