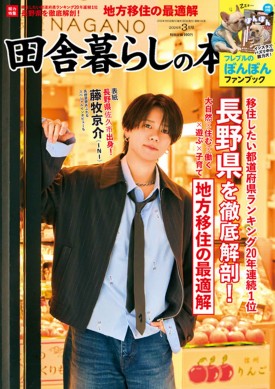畑の肥料に人間が排泄したもの、すなわち屎尿を利用していた時代
屎尿が肥料だった時代の農業から学ぶこと
玉ネギ、ニンニク、ソラマメを植える準備に追われている。今日はそのうちの玉ネギだ。左右を秋ジャガとミョウガに挟まれた場所。6月から8月にかけて、大汗かいて抜いたり引きちぎったりした夏草を積み上げた。それがほぼ腐食を完了し黒々とした良質の土になっている。
問題は地下を這う篠竹。細いものは腰を下ろした姿勢でスコップで掘り取れる。しかし太いもの、長く横に這ったものはスコップでは不可だ。4本刃の鍬をフルパワーで打ち込む。この作業を頑張りすぎると夜、寝返りを打つ時に背筋がビリビリすることがある。
八割がた土に同化した夏草を手でさらいながらふと思い出したこと。パンツを土に埋めて土壌の微生物の働きを知るというスイスでの話。科学者の呼びかけで1000人が参加したらしい。埋めるパンツは100%の綿製品。数週間後に掘り出して腐食の程度を観察・・・。なるほど、僕もいつかやってみようと思う。
「朝日新聞写真館since1904」をいつも楽しみに読む。自分が生まれたころから中学生時代くらいまで、日本という国のさまが数枚の写真を通して目の前に現れる。今回注目したのは1946年(昭和21年)、東京郊外に到着した「汚穢専用列車」、そこに集まった農家の人たちの姿。
戦後の肥料不足で屎尿の需要が高まった。人間の排泄物を木製のタンクに詰めて専用列車で運んだのだ。都内の処理施設には郊外から馬車や牛車、リヤカーが押し寄せたという。
汚いことが平気な僕だが、ひとつ想像する。見知らぬ人が出したウンチやオシッコをタンクに詰めて持ち帰る、当時の農家の人たちはどんな気持ちだっただろうか。くさい、汚いなんて気持ちはなく、うちの野菜たちが喜ぶ、それだけだったのだろうか。
時代の進歩がここにもある。戦後80年の今、ホームセンターにはきれいな袋に入れて積み上げられたさまざまな肥料がある。大量購入者には業者が農家の畑まで運搬してくれる。人間が排泄したもの、ウンチやオシッコは栄養豊富だが、問題はその保管であり衛生管理だ。化学肥料万能という今、人糞で野菜が栽培されていたなんて知る人はいずれいなくなるに違いない。
買うってことは、自分を高める機会と縁を切ることでもあると思うんです
買う・持つ・作るの価値基準を問い直す
天気予報では晴れだった。しかし大ハズレ。気温も低く、終日雨であった。なんと、北の方では農家への霜注意報も出ているらしい。この先どうなるのか予測不能。しかしまあ、愚痴をこぼすだけではしょうがない。雨多く、光なく、気温も低い。そんな悪条件の中でどうすれば野菜たちを成長させてやれるか。この思案と苦心をどこかで僕は楽しんでもいる。
今月初めに植えた白菜は支障なく育っている。先月植えた白菜は暑さに苦しめられた挙句、徹底的に虫に食われて無残。そうそう、ひとつ気が付いたことがある。このすぐ上の写真の奥の方、ビニールハウスのパイプが見える、そこに植わっている白菜は写真手前のグループよりも成長が一段早いのがおわかりか。
植える直前までこのハウスはビニールで完全に覆われていた。風通しをよくするために両サイドをまくり上げ、天井部分に固定した。つまり、残った天井部分のビニールが防寒の役目を果たした。同じ日に植えたのに、丸出しの白菜より日数で言うと20日ぶんくらい成長が進んだ。植物は、ほんのわずかな環境条件の違いに対応するのだということを僕は知る。
雨の中、庭のあちこちに散乱したキウイを拾い集める。今年の猛暑の影響なのか。例年になく途中落果するものが多い。そのまま生食するには糖度が低い。でももったいないね、このままでは。ハチミツをたっぷり入れる。水分の多い果物だから弱火で3時間も煮ればできあがる。
買うってことは、自分を高める機会と縁を切ることでもあると思うんです。(足立繁幸)
足立繁幸という方は、DIYによる場所づくりに取り組む人であるらしい。鷲田清一氏は「現代人は生活に必要なものを一から自分で作るより、既製品を購入したり作業を外注したりして、金銭で賄う。が、そのことで生きているというヒリヒリした感覚も、物から届く生々しい情報も見失ったのではないか・・・」そう解説する。
僕もカネを出してモノを買うことはある。しかし、会社勤めの人なんかに比べればDIYの機会は多いのではないか。前から書くように、家の修理は定期的にやっている。また太陽光発電のバッテリーを置く場所、寒さに弱い植物を置く場所、仕事で使う資材を置く場所、そんな小屋をこれまでに6つ作った。
どれも自慢できるような仕上がりではないが、鷲田清一氏が言うように「生きているというヒリヒリとした感覚」を常に伴う。3メートルの柱を立てて横木と組み合わせる・・・そんな作業では大なり小なりの傷を手に負う。そのヒリヒリ感であると同時に、自分の手で何かを作る、そこにはたしかに精神のヒリヒリ感がある。
野菜や果物の自給も一種のDIY だと言ってもよいか。先ほど書いたが、猛暑の後は雨ばかりの日々で低温。それになんとか立ち向かう。雨対策、低温対策はかなりの手間と時間を要するが、トライ10のうち、たとえ成果ありが3つだとしても、やったぜの手応えは得られる。田舎暮らしという生き方はまさにDIY。切り傷や蜂に刺されたヒリヒリ感とともに、自分の知恵と力で暮らすヒリヒリ感がなるほどそこにはある。
この記事のタグ
この記事を書いた人
中村顕治
【なかむら・けんじ】1947年山口県祝島(いわいじま、上関町・かみのせきちょう)生まれ。医学雑誌編集者として出版社に勤務しながら、31歳で茨城県取手市(とりでし)に築50年の農家跡を購入して最初の田舎暮らしを始める。その7年後(1984年)の38歳のとき、現在地(千葉県八街市・やちまたし)に50a(50アール、5000㎡)の土地と新築同様の家屋を入手して移住。往復4時間という長距離通勤を1年半続けたのちに会社を退職して農家になる。現在は有機無農薬で栽培した野菜の宅配が主で、放し飼いしている鶏の卵も扱う。太陽光発電で電力の自給にも取り組む。
田舎暮らしの記事をシェアする