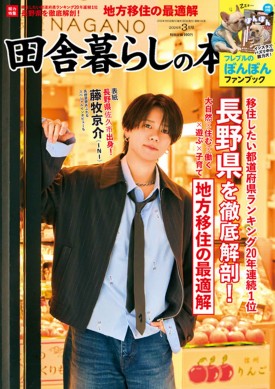「負動産」がチャンスに?変わりゆく時代の田舎暮らしと農地活用の可能性
農業と人生から学ぶ「まっ、しょうがない」の境地
「努力をすれば報われる」という言葉には一片の希望がある。そして危うさがあることもまた確かだ。何かをきっかけにして、それはくるりと自己責任論に転じ、「苦境にあるのは努力が足りないからだ」と他人へのきびしい目となる・・・。
しばらく前に目にした天声人語の冒頭部分。天声人語は続けて安倍総理時代、自民党支持者への聞き取りを紹介。「格差社会は仕方ない。努力した人生は否定されるものじゃない」「自分のことは自分で守るのが当たり前」そんな発言が多かったという。政治的なことは今はさておく。百姓暮らしにおいて、まず、なすべきことは全てなす。その努力が実らなかった時、まっ、しょうがない。次はもうちょっと工夫してみよう、これが我が生き方・・・。この話には続きがある。「努力」をキーワードとした米国民主党支持者と熱狂的なトランプ支持者との隔たり。でもひとまず今は置く。
0円物件の登場と自治体の変化
トシ取ると時代は変わったと思う場面が多くなる。世間の注目を集める歌や役者を知らない。50歳くらいまで熱中したマラソン大会。維持費の高騰や参加者減で消滅するものが多いというニュースにも驚く。しかし、なんたって一番驚いたのは他ならぬ田舎暮らしと関わる事柄。
朝日新聞の『現場へ!』が「限界不動産」を5回連載。アナタはご存じか。親から相続するも資産価値なし。でも維持費はかかる。もって”負動産”という言葉が生まれた。維持費さえかからねば物件はタダでいい。インターネットのサイト「みんなの0円物件」や「負動産の窓口」はこうした事情から発生したものらしい。
僕が驚いたのは、うるさいことを言わない、柔軟な対応をする自治体が増えたという記述。農家以外が農地を取得するには農地法によって地元の農業委員会の許可が必要だ。今から40年前、僕が現在の畑を買おうとするとき農業委員会に呼び出された。耕作経験を細かく問われ、本気で農業をやろうとしているのか、投資目的ではないのか、厳しい質問を浴びせられた。
そんな過去の経験ゆえ、朝日新聞に紹介されている事例に時代は変わったという感慨を深くしたわけだ。かつて、土地は間違いなく価値ある財産だった。だが人口は減り、地価上昇は大都市圏か外国人に人気のあるスキーリゾート地だけとなった。親から引き継いだ農地を懸命に守ってきた人たちも高齢となり、生活インフラの消滅などで生活そのものの維持さえ難しい。それゆえ農地を手放したいと考える高齢者は多い。朝日新聞の記事にはタダで農地を手に入れたという人が登場。まさしく、田舎暮らしを夢見る人にとって今は大きなチャンスであろうと僕は思う。
猛暑と戦う「自然派」の生き方
なぜそれでも「不便益」を選ぶのか
ついに猛暑の王様が登場した。気温36度。無風。畑でスコップ仕事をすると、熱を持った綿の中に埋もれているようだ。しかし日中はまだいい。夜の気温27度。窓2つを開けたまま、パンツ1枚、50センチの距離に扇風機を「強」で朝まで回す。窓を開けたままゆえ蚊が入る。が、扇風機が蚊を吹き飛ばしてくれる。
ふだんから口の悪いガールフレンドが言う。バッカじゃないの、こんな暑さで昼間10時間働き夜は扇風機・・・原始人だよ、自分のトシを考えろ、いまに死ぬよ。エアコン買いな。高いものじゃないよ。いいかい、今のままじゃ死ぬよ・・・。
ふふっふ。少しは愛を込めた言葉。でも相変わらずキビシイねえ。エアコンの心地よさはスーパーで知っている。でも買う気にならず。だってエアコンの心地よさを体が覚えたら日中のスコップ仕事なんてやる気にならない。
それよりも、寒さを含め、自分の体が自然に対してどこまで通用するかを確かめたい。僕の主治医は僕自身。呼吸、心臓の鼓動、脈拍、仕事しながら常に観察。先に、食べ物に関して優れたカンがあると書いたが、自分の体への観察力も優れていると思う。でも我が体もいつか耐用年数は来る。しかしその日が来るまで“この苦しみ”を楽しみとして生きてみる。
猛暑の畑に潜む影
アライグマ被害を防止するためネットを張ったトウモロコシが食われた。2メートル近いネットを乗り越えたか、僕が気付かない穴がどこかにあるか。猛暑の中、今日はトウモロコシそのものに上からネットを掛ける作業に奮闘した。
この記事のタグ
この記事を書いた人
中村顕治
【なかむら・けんじ】1947年山口県祝島(いわいじま、上関町・かみのせきちょう)生まれ。医学雑誌編集者として出版社に勤務しながら、31歳で茨城県取手市(とりでし)に築50年の農家跡を購入して最初の田舎暮らしを始める。その7年後(1984年)の38歳のとき、現在地(千葉県八街市・やちまたし)に50a(50アール、5000㎡)の土地と新築同様の家屋を入手して移住。往復4時間という長距離通勤を1年半続けたのちに会社を退職して農家になる。現在は有機無農薬で栽培した野菜の宅配が主で、放し飼いしている鶏の卵も扱う。太陽光発電で電力の自給にも取り組む。
田舎暮らしの記事をシェアする