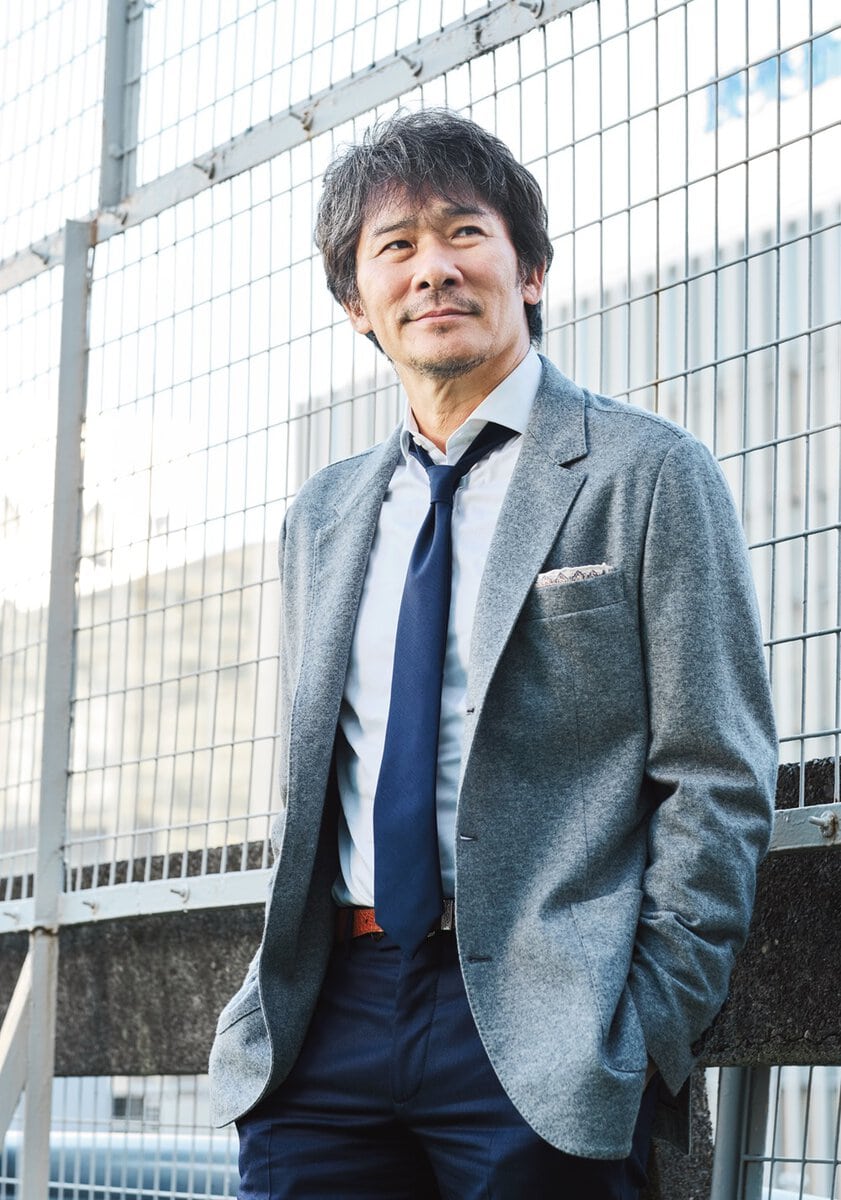どこか日本人離れしたスタイルとスケールの大きな演技を活かし、近年は海外作品にも積極的に取り組んでいる俳優の伊原剛志さん。フランス人女性監督エリーズ・ジラールによる映画『不思議の国のシドニ』に出演、国際派女優イザベル・ユペールと共演しています。映画のこと、多彩な趣味のこと、役者としての現在について、伊原さんに伺いました。
掲載:2025年1月
いはら・つよし●1963年福岡県生まれ、大阪府出身。1983年に舞台で俳優デビュー。『硫黄島からの手紙』以降、クライヴ・オーウェンと共演した『ラスト・ナイツ』、ブラジル映画『汚れた心』『ヤクザプリンセス』と海外作品にも多く出演。最近の主な出演作は『ストレイヤーズ・クロニクル』『家族の日』など。主演映画『ら・かんぱねら』が公開待機中。
全編フランス語のセリフと格闘
「最初はフランス映画というのと大まかな内容しかわからず、台本もなくて。それで監督が日本の俳優さん何人かと面接をするらしいと。僕がいちばん初めだったのかな? 1時間ほどお話ししたのを覚えています」
そう教えてくれたのは、『不思議の国のシドニ』に出演した俳優の伊原剛志さん。全編フランス語のセリフと知ったのは出演が決まってから。クリント・イーストウッド監督の『硫黄島からの手紙』以来、英語での演技は経験を積んだものの、ゼロからのスタートだったフランス語を、8カ月かけて猛特訓することに。
「ゆっくりとちょっとゆっくりめと普通、3段階の速さでセリフを読んだ音声を用意してもらい、まずそれをひたすら聞きました。最初はそれでも全然わかりません。ただ、フランス語の先生が英語を話す方で、日本語より英語のほうがフランス語に近い。それで〝これは英語だと何て言うの?〞などと聞くとわかりやすくなりました。英語で芝居することには慣れてきましたが、それがフランス語になった感覚です」
伊原さん演じる溝口健三は書籍の編集者。デビュー小説が日本で再販されることになったフランスの作家シドニが、プロモーションで来日することに。彼女をアテンドして寺や日本庭園を巡る。
「溝口は、あるタイプの日本人。シャイで、ちょっと心を閉ざしている。最初サングラスをかけているのは台本に書いてあったのかな。それでいて、自分なりのポリシーを持っている男で」
初対面のお辞儀に始まり、無口で、何を考えているのか今一つわからない。それでいてどこか堂々としてもいて、女性の扱いも武骨ではない。そんな役柄の溝口は欧米人の目に映る日本人像のようでいて、フランスの大学を出た設定のせいか、日本人の目には欧米人のようなスマートさも備えたように映る。
「ああ……それは僕が演じたせいかも。海外で仕事をすると、『日本人らしくない』とよく言われるんですよね。がたいがいいし、自分の意見をしっかり言うし……って、どうなのだろう? 自分ではよくわからないけど、どっしり構えていて物怖じしない? 女性には椅子を引いてあげるし、ドアも開けてあげるしね!」
「それ、日本の男性は大抵しませんよね?」と言うと、「僕もそうでしたよ、はははは」と笑い飛ばされる。 劇中には彼女のハンドバッグまで持ってあげて、シドニを慌てさせたりするシーンもある。
「あれは監督が初めて日本に来たときの体験みたいですよ」と伊原さん。そうして京都、奈良、直島(なおしま)とシドニの目を通し、こちらまで日本の文化と出合い直すよう。
「奈良の大仏には朝早くに行ったのですが、まだ観光客なんて、誰もいなくて。シーンとしていて気持ちよかったです。僕は大阪出身なので、昔遠足でここに来たな〜と思い出したりして。直島には初めて行きました。あそこはフランス人が好きなんですって。現代アートの聖地とも呼ばれていて、アート好きな人が行くだろうから、余計に島を好きになって帰るんでしょうね」
シドニを演じたのはフランスの名女優、イザベル・ユペール。
「芝居をする、そのオンになったときの集中度はすごい。でも、オフになると普通で、撮影終わりにみんなで食事に行ったりしました。イザベル・ユペールと芝居をするから緊張する、ということは全然ないです。僕の好きなロバート・デ・ニーロでもないと思います。若いときは、こんな人と!?と緊張しましたけどね。ただその役と役で対峙する、それだけです」
それならいろいろな生活習慣や文化を持つ人と、映画というツールを通してセッションしたい――。その思いが、積極的に海外に出ていく原動力となる。
しかも、最初がイーストウッド監督の作品。伊原さんは役の最期を、「こんなふうに演じたい」と監督にアイデアを提案して採用されたそう。エルメスのブーツを履いていたという資料を見つければ、スタッフはそれを用意する。待遇を含め、最高の現場だったという。
「いいと思うことは言う。もちろん却下されることもあるけど、『なるほど』と思えばそれを受け入れ、『そうじゃない!』と思ったら食い下がる。このやり方は自分に向いているなと。つまりは、その役をどう捉えるか? お前はそう考えるのか、俺たちはこうだ、そんなセッションです。日本では意見を言わないことが『よし』とされたりするけど、海外で〝up to you(お任せします)〞と言うと、何も考えてないの?ということになる。でも、日本でそれだとtoo much(度が過ぎている)だから、うまくバランスを取りながらです。それでもやっぱり、カメラ前で役者がすることは同じ。やりたいことがあって、そこに持っていくための方法が違うだけ。それで今回はフランス人の監督、そしてイザベル・ユペールと3人、〝セッション〞しながら撮影しました」
一生懸命に楽しみ、一生懸命にトライする
「僕らは多かれ少なかれ死者とつながっている」、映画にはそんなセリフが登場する。開かないはずのホテルの窓が開いていたり、手をつけていないお弁当がキレイに食べられていたり、夫を亡くしているシドニの周囲で不思議な出来事が起きる。京都の寺で枯山水の庭を眺め、直島の海辺に立って、異国での静けさのなか、シドニは愛の喪失と孤独にもう一度向き合う。
「祖先が守護霊として自分を守ってくれる、日本人のそんな感覚は、西洋の人には不思議なものかも。僕にもこんなことがありました。1歳に満たないころに何カ月も熱が下がらなくて。お祓いをしてもらったら祖先の霊が出てきて、『その人を供養してください』と。それで供養したら熱が下がったらしいです。霊媒師を通して死者を蘇らせるとか、そうしたことを信じるわけではありません。でも、亡き母がふとしたときに夢に出てくるなんてことは、誰にでもありますよね」
伊原さんの母親は、とても元気な人だったそう。
「60歳くらいのとき、ちょうど今の僕ぐらいのころはいろいろな習い事をして。晩年はお見合いクラブに入り、2人の男性と付き合ってましたから!〝1人はアッシー君〞とか言って(笑)」
そんな母親の背中を見ていたせい? 3人の息子の父親でもある伊原さん自身、「なんでいつも楽しそうに生きているんだろう?」、そう思わせる背中を見せるのが、父親としてのいちばんの務めだと考える。「それって難しくないですか? 特に厳しい世界でもある役者さんの場合は」と尋ねると、「だから息子たちは誰も役者になってないですよ」と笑う。
「基本はやっぱり、なんでも楽しむことだと思うんです。一生懸命に楽しむ。一生懸命にトライする。そもそも僕自身、挑戦することが好きなんですよ」
英語や今回のフランス語だけではない、ボクシングも落語も。さらに次回作の映画『ら・かんぱねら』では、これまたゼロの状態からピアノを習い、フジコ・ヘミングの愛した難曲に挑んだ。
「〝これくらいはできるだろう〞と思えることより、トライしないといけないものに燃える。普段の自分は何もしないから、やらないといけないからやるか……と、仕事にかこつけて自分にムチを打つと。これは性格的なもので。それでやり遂げたときに、褒められるのが好きです(笑)」
SNSには、生け花を楽しむ姿も。なんて幅の広い!
「男3人で体験したら面白かったんですよ。それで僕だけが続いています。小さいころはプラモデルをよくつくっていたんです。帆船が好きで、そればっかり。生まれ変わったら建築家になりたい!と思う時期もあったんです。たまたま、息子の1人はその分野に進みましたけど」
YouTubeでは、矢沢永吉ばりの歌声でシャウトする姿も披露。これまた「生まれ変わったらミュージシャンに」と伊原さん。「役者は1時間2時間かかるところを、4分ほどで人を感動させる。ミュージシャンって尊敬します」と。
「やりたい!と思ったことはなんでもやる、やってみる。何をやりたいかがいちばん大事です。そうしてまず、本当にやりたいことを見つけるのが最初の幸せ。次に、それを仕事にして暮らせるようになれば、なおかつ幸せ」
そこに関して、伊原さんは計画的で行動力があった。居酒屋でバイトをして70万円を貯め、高校卒業と同時に夜行列車で上京。俳優として軌道に乗ってからも、どうしたらいい役者になれる?と考え続け、お金の心配をせず俳優業に打ち込むため、お好み焼き店を開業。外食チェーン店にまで成長せ、なんと、17店舗も展開させた。
経営からはすでに身を引くも、目標を定め、こうと決めたらやり通す。そうして今を全力で楽しむ姿は、途方もない現実的な努力の積み重ねがあればこそ。そんな父親の背中は、息子たちに多くを語ることだろう。
「悪戦苦闘しつつ、いろいろなチャレンジをし、失敗を含めてそのすべてを楽しむ。それが生きるエネルギーになる気がします」
次なる挑戦は、漫才。盟友である俳優の川平慈英さんと組んで、本気で笑いを取りにいく。
「楽しいことをやろう、一緒に舞台でも?という話になって。役者に挑戦するお笑いの方は多いけど、その逆ってないと思わない? それだ!と盛り上がって。今着々と進んでいます」
60代の今、演じることが楽しい!
「この雑誌、たまに読みますよ! ネットで0円物件を調べたり、田舎暮らしには興味あるんです」
現場に現れた伊原さんは、開口一番にそう教えてくれた。
「たまたま今朝、今の家を売って田舎に行ったら、もっとリッチな暮らしができて、空気もおいしいし……なんて話をしたんです。今やどこでもネットでつながれるし、仕事のときだけ東京に出てくればいい。もともとあまり家には固執しないんです、気持ちはいつまでもバックパッカーで。どこにでも行ける身軽さを好みます。小さい犬を飼っているので、何匹か飼えるのはいいなと思うけど」
60代を迎え、意識の変化を感じている。
「子育ても終わって肩の荷が下りたというか、より自分にフォーカスできるようになりました。自分の思うままに生きていける、ようやくそんな年齢になったのかもしれません」
そうしてあらためて感じるのは、芝居って楽しい!ということ。
「最近も舞台をやったのですが、若い人はセリフを覚えるのも早いな!と驚いたり、自分が思うように演じられずに落ち込んだり。それで今になって、役者に向いてないな……とか(笑)。基本的には、自分じゃないところで生きたいんですよね。その役の世界、それを想像しながら空想の中で生きていけるのが楽しい」
人生を振り返って昨年、20代前半で出会った恩師、坂東玉三郎さんとの再会も果たす。出会いは、玉三郎さんが舞台の演出をした作品のオーディション。自宅で演劇の勉強をしたり、台本の読み方をイチから教えてもらったり。プライベートでもお世話になるも、「不義理をしてしまって」、会わないままに月日が過ぎていた。
「自分の人生、役者人生にとってかけがえのない方なので、ちゃんとお話ししたいと思ったら会ってくださった。〝僕も大人になりました〞と言うと、〝会いに来てくれてうれしい〞と喜んでくださって」
いったん疎遠になってしまった恩人に長い時を経て会いに行くなんて、そう簡単ではないだろう。でもそんなふうに縁を大切にする人だから、人との出会いに恵まれるのかもしれない。そう言うと、「ずうずうしいのかな」と笑っている。
そうして今も変わらず仕事には全力で取り組み、時には本気で落ち込むも、今までよりずっと楽しい!と言えるなんて。なんてすてきなことだろう。
「この先、どこまで行けるかわかりません。でも、ただのおっさんにならないように。若くいることではなく年相応に格好よく生きたい。そう思っているんですよね」
『不思議の国のシドニ』
(提供:東映 配給:ギャガ)

© 2023 10:15! PRODUCTIONS / LUPA FILM / BOX PRODUCTIONS / FILM IN EVOLUTION / FOURIER FILMS / MIKINO / LES FILMS DU CAMELIA
●監督:エリーズ・ジラール ●出演:イザベル・ユペール、伊原剛志、アウグスト・ディール ほか
●12月13日(金)よりシネスイッチ銀座ほか全国順次公開
フランス人作家シドニ(イザベル・ユペール)は、出版社の招きで日本へ。編集者である溝口(伊原剛志)のアテンドで、取材をこなしながら京都、奈良、直島へ旅する。ある日、滞在先のホテルで、亡くなったはずの夫アントワーヌ(アウグスト・ディール)が姿を現す。その夜、夢にうなされて目覚めたシドニがホテルのバーへ降りていくと、そこには溝口がいた……。
文/浅見祥子 写真/鈴木千佳 ヘアメイク/山岸直樹 スタイリスト/柴崎 篤
この記事の画像一覧
この記事のタグ
田舎暮らしの記事をシェアする