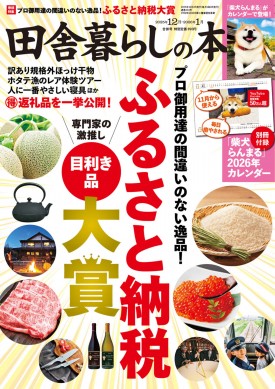5月2日「ニワトリは3歩あるいたらもうさっきのことはもう忘れている・・・なんて、あの言葉はウソだよ、ほんとはとても頭のいい動物だよ」。
昨日とは打って変わって快晴の今日である。ビニールハウスを組み立てる。トマトとゴーヤを植えるつもり。廃材を利用していつも通り、行き当たりバッタリの作業だが、最長10メートルくらいまでの面積は確保してある。
ここは先月まで大根があった場所。そこを整地すると、早速ニワトリたちが集合する。ニワトリたちの状況察知能力はとてもすばらしい。前に書いたように、鍬かスコップを僕が手にして歩き始めると、それっ、虫だぞとばかり後を追う。すぐ足元に来られては作業がやりにくいので、彼女たちに悟られぬよう、わざと遠回りして現場に行くこともある。しかしそれも見破られる。どうやら鍬やスコップを使う、その音を聞きつけるらしいのだ。そして、1羽か2羽が僕の方向に走ると、遠くにいた連中もその動きを察知して、結局この下の写真のようになる。ニワトリは3歩あるくともうさっきのことは忘れている・・・どこの誰が言ったことだが知らないが、とても失礼な言葉である。その証拠に、2か月ほど前になるか。鶏舎のわずかな隙間からタヌキが侵入、深夜にニワトリを襲ったことがある。その翌日から、小屋には誰も寝なくなった。軒下に5羽、玄関の箱の上に3羽と分散・・・それは明らかに、昨日の恐怖を忘れず記憶しているという行動だった。頭は悪くないどころか、とてもいい生き物なのである。
5月3日「どこまでも愛にあふれるひたむきな生涯」。
6時20分起床。5月ではあるが、朝の空気はまだかなりひんやりする。しかし、これぞまさしく五月晴れ。昨日に勝る天気。何という心地よさか。光と風のバランスのよさか。さて働くぞ。昨日半分まで進んだビニールハウスの組み立て。今日のうちに完成させたい。設計図なし。次はどんな形で、どのくらいの長さのパイプがあればよいか。それを目分量で確かめてから倒壊した別のハウス現場に行き、曲がったり折れたりしているパイプを取り外して調達する。
午前中でパイプの接続が完了。ランチをしてからビニールをかぶせる作業に移る。半年間ずっと、イチゴやエンドウの寒さ除けに使ってきたビニールは泥だらけだ。それをまずかぶせてから、30メートルのホースを引っ張り、外部と内部に水を放射する。まだ汚れは取れていないが、まずまずの仕上がりだな。
3時のお茶タイム。珈琲をいれ、ハウスからつまんで来たイチゴと小さなケーキを口に押し込みながら一息ついているところに、3日前に孵化したヒヨコを連れたママが通りかかる。チャボの母親はどれも愛情豊か、育児にひたむき。その中でもこのママは群を抜いてひたむき。覚えておられるか、以前書いたことを。昨年4月。岐阜から届いたヒヨコ30匹。まだ気温が低く、僕はパソコン部屋に育児室をこしらえ、電気カーペットで暖かくしてやった。10日間ほどは外には出さず、水やり、餌やり、運動も部屋の中。当然ながら床は汚れ放題だが、そんなことは気にもせず、これまた「ひたむき」、目の前のことに突き進むのが中村流。そして、どうにか寒気も去って、そろそろ光と外気に当ててやらねばと庭に出した、そのヒヨコたちの面倒を見てくれたのが、この下の写真、今3匹のヒヨコを連れて僕の目の前にいる黒いママだったのである。
僕がこれまで経験したチャボの中で、最も多い数のヒヨコを育てた例は14匹だ。生後半月もすると自分のおなかに14匹がスンナリ入りきらない大きさになる。しかしこの黒いママは、岐阜から届いた30匹を見事に育て上げたのだ。昼間はまだ良かっただろう。問題は箱に入って眠り態勢になる夕刻だ。30匹がいっせいにママのおなかにもぐり込もうとする。もぐり込めないものは背中に乗る。そんな日が1か月以上も続いたのだ。その苦労やいかに、体力的なシンドさはどれほどのものであったか。しかし彼女はイヤな顔ひとつせず、むしろ僕には、子だくさんの育児を楽しんでいるようにも見えた。思うに、チャボ・ニワトリの「人生」とは、食べること、砂浴びすること、そして子を産み、育てることだけである。雌のチャボは、ハヤブサなどに襲われて死ぬというアクシデントがない限り、この抱卵・育児というサイクルを生涯に20回ほど経験する。多くの子孫を残す。そしてやがて老いてゆく。
この記事を書いた人
中村顕治
【なかむら・けんじ】1947年山口県祝島(いわいじま、上関町・かみのせきちょう)生まれ。医学雑誌編集者として出版社に勤務しながら、31歳で茨城県取手市(とりでし)に築50年の農家跡を購入して最初の田舎暮らしを始める。その7年後(1984年)の38歳のとき、現在地(千葉県八街市・やちまたし)に50a(50アール、5000㎡)の土地と新築同様の家屋を入手して移住。往復4時間という長距離通勤を1年半続けたのちに会社を退職して農家になる。現在は有機無農薬で栽培した野菜の宅配が主で、放し飼いしている鶏の卵も扱う。太陽光発電で電力の自給にも取り組む。
田舎暮らしの記事をシェアする